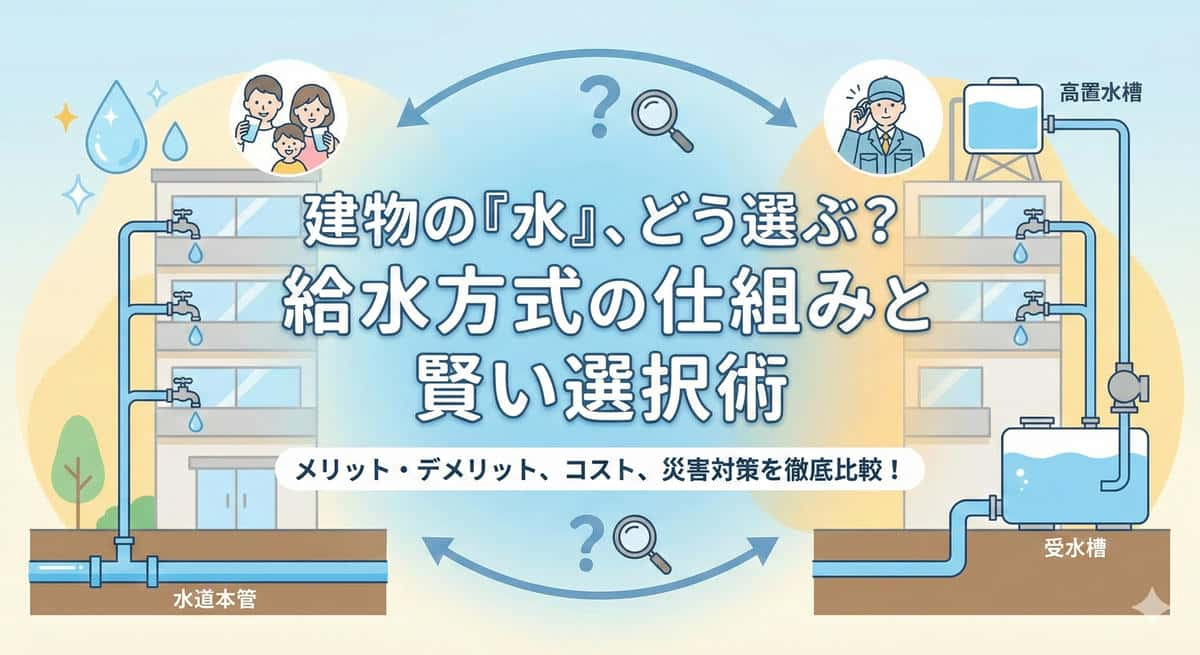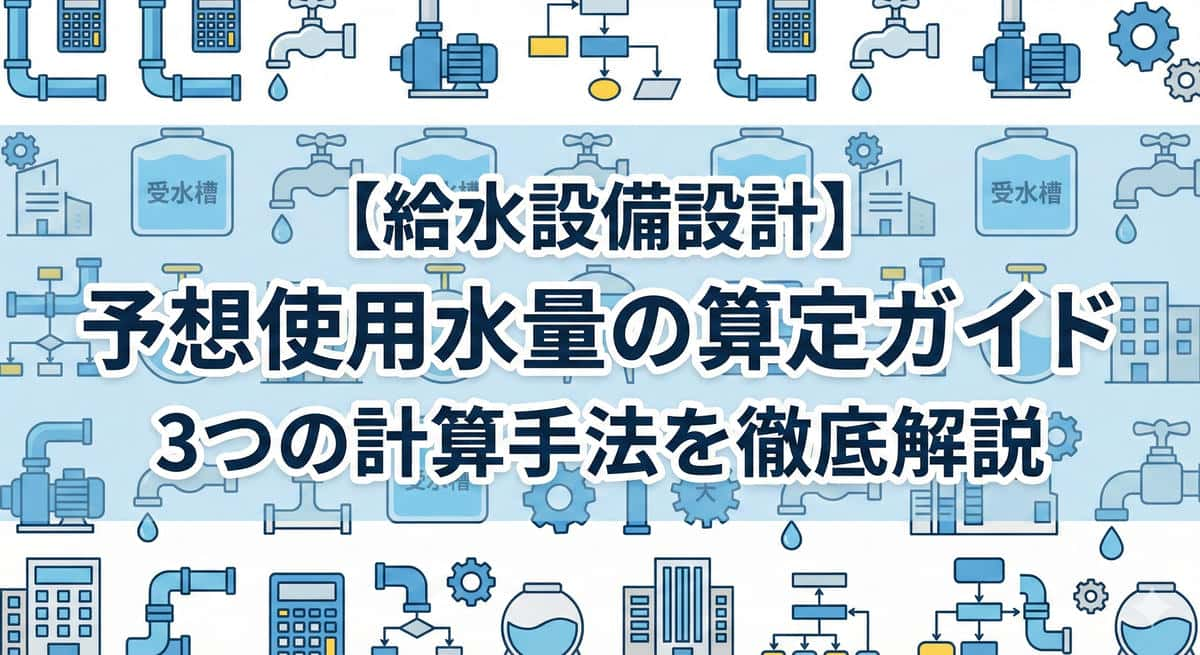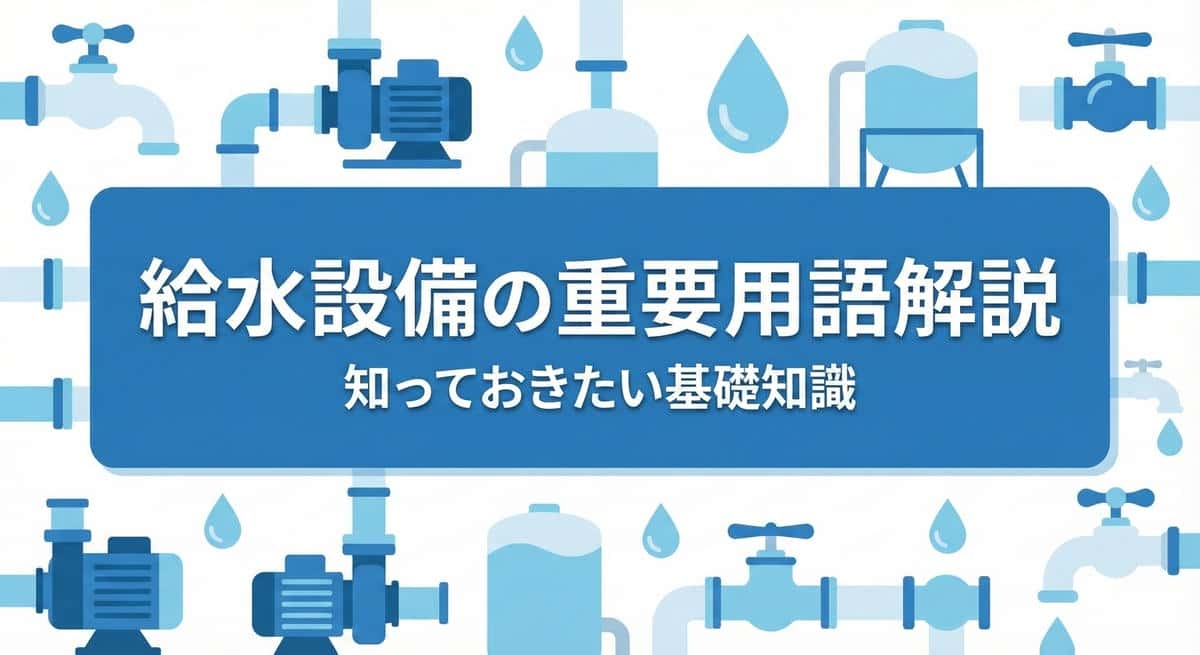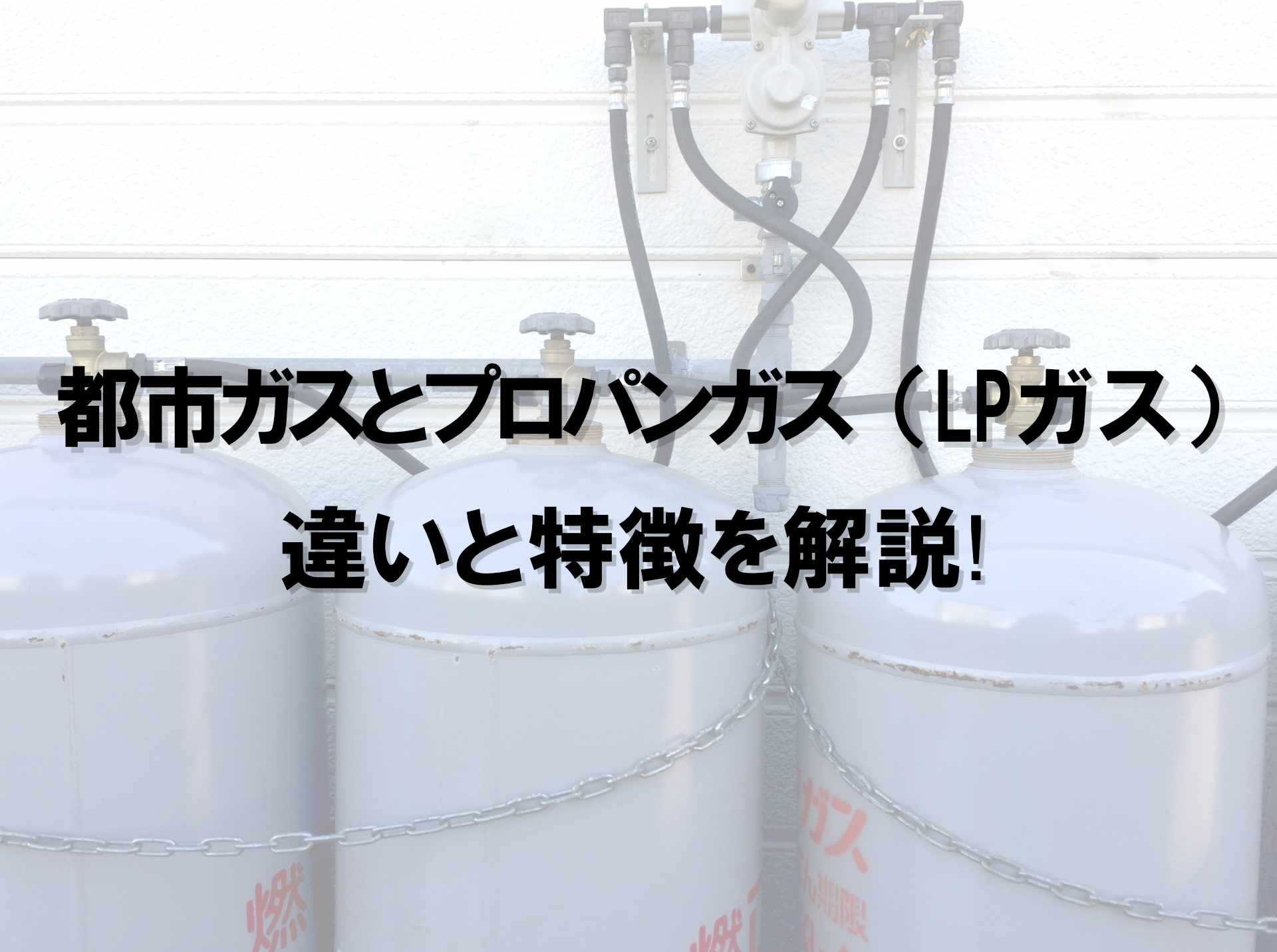上水道と下水道の基本-普及率や法規制

衛生設備の話をするうえで欠かせないのが、上水道と下水道です。
上水道と下水道の基本をざっと見ておきましょう。
上水道の基本
上水道とは、一般的に「水道」と言われているものとほぼ同義で、飲料可能な水の公共的な供給設備のことを言います。
日本の水道普及率は2018年で98%に達しています。
普及率が100%の都道府県が、東京・大阪・沖縄で、最低が秋田の91.4%です。
(H30.3月現在:厚生労働省 水道の基本統計)
水道水の水質基準
水道水は、河川や井戸などから水を取り、浄水場で浄化してから一般の家庭などに送られます。
そのため、取水する川や湖の水質が悪化すると、凝集剤や滅菌・消毒用の薬物が多く注入されることになります。
水道水は水質の基準が厚生労働省で決められています。
上水道の水質基準は以下の3種類を覚えておきましょう。
- 水質基準項目(51項目)
- 水質管理目標設定項目(26項目)
- 要検討項目(44項目)
①水質基準項目(51項目)とは
水道水として基準値以下であることが求められる項目であり、水道法により検査が義務づけられているものです。
健康関連31項目と生活上支障関連20項目で成り立っています。
②水質管理目標設定項目(26項目)
今後水道水中で検出される可能性があるなど、水質管理上留意する必要がある項目です。
健康関連13項目と生活支障関連13項目で成り立っています。
③要検討項目(47項目)
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
今後、必要な情報・地検の収集に努めていくべき項目です。
水質基準の目標値などの詳細は、厚生労働省のHPで確認ができます。
水道の種類について
水道にもいくつかの種類があることを知っていますか?
大きくは4つに分けられます。
水道事業・・・水道事業は簡易水道事業と上水道事業に分かれます。
簡易水道事業・・・給水人口が101人以上5000人以下である水道により、水を供給する水道事業です。
上水道事業・・・簡易水道事業以外の水道事業です。(給水人口5000人以上)
専用水道・・・寄宿舎、社宅等の自家用水道等で100人を超える居住者に 給水するもの又は1日最大給水量が20m3を超えるもの
簡易専用水道・・・他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものです。
水道用水供給事業・・・水道事業者(水道事業を経営する者)」に対して水道用水を供給する事業です。
下水道の基本
下水道とは、下水を公共用水域へ排出するための施設・設備です。
そもそも下水とは何を指すのか確認しておきましょう。
下水には汚水・雑排水・雨水の3つの種類があります。簡単に説明すると、
- 汚水・・・し尿を含む水
- 雑排水・・・し尿を含まない水(洗濯機やお風呂の排水など)
- 雨水・・・雨が降った後の水
下水道の処理方法には2種類ある
下水道には合流式下水道と分流式下水道の2種類があります。
合流式下水道
合流式は汚水・雑排水・雨水を合流させて一緒に流します。
合流式では雨水も一緒に終末処理場に入ることになるため、大雨の時は処理しきれなくなり、一部をそのまま河川や海に流すことになります。
配管が一系統で工事費も安く済むため以前は多く採用されていましたが、環境に対しては悪影響もあるため、新設の場合はほとんど採用されることはありません。
分流式下水道
分流式は汚水・雑排水を汚水管、雨水を雨水管に分けて流します。
公共下水道のない地域では、排水をし尿浄化槽で処理した後に公共用水域へ放流します。
下水道については、公共下水道が施設されているか、公共下水道が合流式か分流式か、し尿浄化槽が必要になるか、必要な場合に単独処理か合併処理かなど地域によって異なってきます。
役所で事前に確認をしておく必要があります。
この記事のまとめ
上水道・下水道は毎日当たり前に利用しているため、あまり意識をすることもないかもしれません。
しかし、人間が安全・便利に快適な生活を送るためには欠かせない設備なのです。